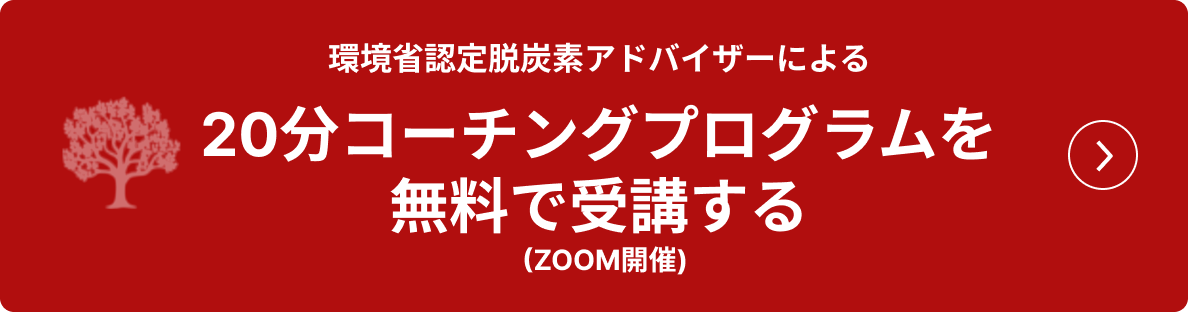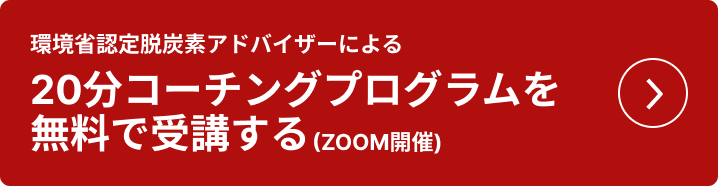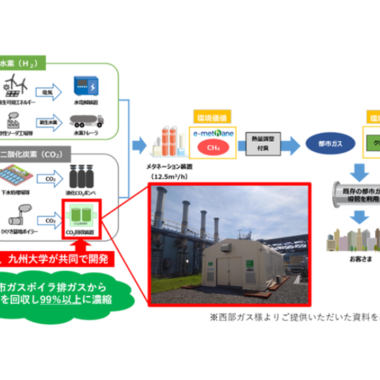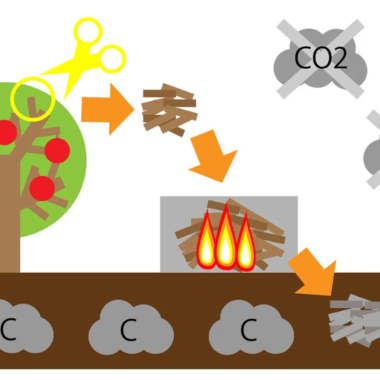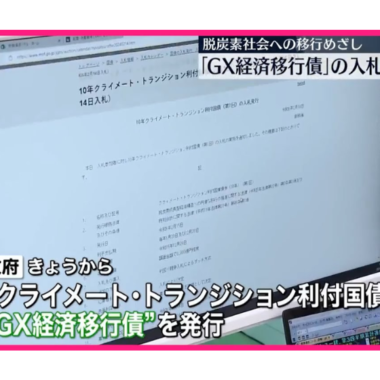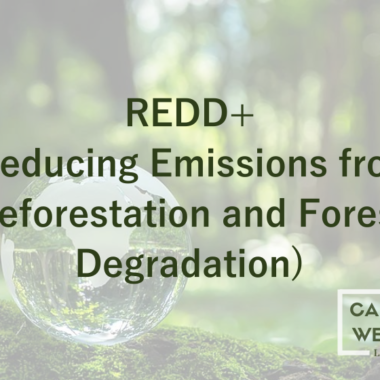太陽光発電協会(JPEA/東京都港区)と再生可能エネルギー長期安定電源推進協会(REASP/同)は6月17日、太陽光発電設備のケーブル盗難対策として成立した「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」を歓迎するとともに、太陽光発電事業者にさらなる対策の強化を呼び掛けた。
「買取らせない」ことでケーブル盗難対策を推進
この法律は、6月13日付で国会にて成立した。盗難ケーブル対策には、「発電所に入らせない、取らせない、買取らせない対策」が必要となるが、今回の法律は、盗品を買取れなくするもの。
具体的には、金属くずの買い取り業者に営業の届出を義務化し、違反した場合の罰則を設けた。また、金属くずの買取時には、本人確認と取引記録の作成・保管、盗品の疑いがある場合の警察官への申告なども義務づけたほか、ケーブルカッターなどのうち犯行使用のおそれが大きな工具を、正当な理由なく隠ぺい・携帯する行為を禁止(罰則あり)するとともに、盗難防止に資する情報の周知徹底が盛り込まれた。
2023年の金属盗難の被害額は130億円以上
警察庁によると、太陽光発電設備からの銅線ケーブルをはじめとする金属の盗難が増加している。2024年の金属盗難の認知件数は2020年の約4倍、2023年の金属盗難の被害額(実務統計)は、130億円以上(窃盗全体の約2割)となっている。太陽光発電設備の被害により、長期間にわたる発電停止による経済的損失も発生している。

窃取された銅線ケーブル(出所:警察庁)
防犯対策の強化と保守運営の再点検を
JPEAとREASPは、太陽光発電設備のケーブル盗難対応について、定期的に注意を喚起してきたが、いまだ全国的にケーブル盗難事故が続発しており、盗難被害は、太陽光発電の特別高圧や高圧設備だけでなく、小規模事業用発電設備や蓄電設備まで拡大しているという。
両者は、ケーブル盗難は、近隣住民の防犯に対する懸念や再エネ電力の供給停止などエネルギー安定供給のほか、地域の安心・安全の面でも無視できない問題だとし、太陽光発電設備を運営・管理している事業者に、以下の対策例を参考に、改めて防犯対策のさらなる強化と保守運営の再点検などの対応を行うよう求めた。
- 設備設計面での配慮・対策例(1)露出(コロガシ)配線はなるべく避ける
(2)地下埋設配管とハンドホールやケーブルラックのロック設計
(3)フェンス・柵・鍵など防犯対策強化、草刈により所内が外から見えるようにする
(4)セキュリティーシステムの導入、侵入アラートシステムによる夜間監視
(5)侵入者に対して警告や光と音で威嚇する設備や記録可能な監視カメラの設置
(6)監視システムのケーブル管路の保護など
(7)アルミケーブルによる配線もしくは張替え(アルミケーブルの設置には、専用端子や専用工具での特殊施工の講習が必要となる。メーカーによる講習会を必ず受けて施工すること)
(8)他国語(クメール、ベンガル、ミャンマー、ベトナムなど)の注意喚起看板 - 運営面での配慮・対策例(1)ケーブル盗難異常検知と緊急駆け付け対応
(2)犯人は必ず下見や事前にセンサー確認を行う。不審な状況が発覚すれば、直ちに最寄りの警察署に通報対応
(3)近隣の人々や発電所間の防犯協力、地域共生の推進による防犯体制の構築(事業者にとっての抜本的な対応が難しい中、近隣の人々との治安協力・地域共生の推進や定期見回りなどで効果を上げているケースもある)
(4)警備会社等を活用した防犯対応強化
(5)動産保険と休業損害保険等の加入による損害対策(防犯対策や対応が不十分な場合には保険が適用されない場合がある。再犯防止を含め、被害を防ぐ対応を十分に行うこと)
太陽光発電普及拡大へ保険契約・運用についても提言
なお、JPEAとREASPでは、今般の損害保険会社による保険引受け条件の大幅見直し、また新規事業における原則盗難不担保の状況が、太陽光発電の普及拡大に大きな懸念となることから、業界団体、保険仲介/リスクマネジメント会社、金融会社・シンクタンクを委員とする緊急タスクフォース(TF)を組成し、抜本的な対策を検討している。
2024年10月には、「太陽光発電の持続可能な保険契約・運用の実現に向けた提言書」「太陽光発電リスク対策チェックシート」「太陽光発電所向け災害・盗難対策ガイドライン」をJPEA・REASP主導で取りまとめ、公表している。
【引用】
環境ビジネス. https://www.kankyo-business.jp/news/f676f47f-9dee-435f-b800-63df93e90f11